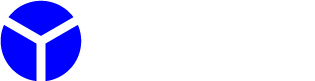8月5日から開始するYDL FPVドローン撮影コースの定員が9名に達しました。
FPV経験者が3人、未経験者が7名であり、映像制作者やドローン事業者、中にはまったく異業種の会社経営者などが今回参加していただきました。
YDL FPVドローン撮影コースは、他のドローンスクールやFPVを教えるスクールと異なり、単にドローンを飛ばす練習場を提供し、基本的な座学を教える場ではありません。実際に他スクールを見た人からすると圧倒的な情報量と講座内容に驚きます。
講座の一例を記載します。
基本講座1:ドローンの仕組み
FPVドローンや自作ドローンを体得するためには、ドローンの仕組みや使用する電波を十分に理解する必要があります。実際の機体を見ながら、「どうしてドローンが動くのか?」を徐々に理解していきます。
・スティックを動かしてからドローンが移動するまで ・2つの無線電波の送受信 ・モーターの回転数と大きさが生む力 ・PIDというループバック制御 ・重心位置x軽さx剛性xモーターパワー=性能など
基本講座2:FPV業務法務
FPV撮影やFPVで企画演出を行う際にポイントとなるのが「航空法」と「電波法」の法規制です。YDLは無線従事者制度を利用するため、免許がなくともコースを受講し実際のFPV機を操縦することができます。今後ご自身でお仕事をする上で必要な法知識を習得し、期間内に免許を取得したり、各種申請の手続きをサポートいたします。
・無線国家資格と総務省開局 ・社団局による複数人同一機器運用 ・無線従事者免許による無免許運転 ・航空法関連業務対応(DIPS) ・JUTM運用調整団体の加入義務 ・対人対物賠償責任保険 ・TV局や大手代理店に求められる誓約書 ・事故における責任の所在はどこにある? ・ドローン事故対応ワークフローなど
応用講座1:無線電波
無線電波は使う周波数帯ごとに特性があり、長距離を飛行させたり映像を遅延なくスムーズにみるために必要な知識や運用方法があります。目的は業務を達成するため。そのためにどのようなツールや運用が必要なのかを実際の業務事例を交えて解説していきます。
・周波数帯が決める距離と伝送容量 ・コンプラと運用の狭間にある電波出力 ・アンテナの長さで周波数がわかる ・立ち位置とアンテナの指向性 ・ロスト時のフェールセーフ対策 ・アナログ無線とデジタル無線など
応用講座2:機体制作・電子工作
FPVドローンを実際に業務で扱う上で自身で機体をメンテナンスしたり制作する技術が必要です。電子工作技術がない人でも、実際に一人で作れるようにサポートします。ドローンを自分で作れるようになれば、撮影以外にも点検に応用したドローンを製作したり、TV番組の企画演出に用いるドローンを制作することも可能です。
・電流Aと電圧Vと出力W ・フライトコントローラ基盤の読み方・調べ方 ・利用するナット・ネジBEST50 ・ケーブルの太さと電流許容量 ・キャパシタとスパイクアブソーバー ・ハンダゴテとコテ先とはんだの使い方 ・予備ハンダの重要性 ・良質なハンダづけを目指すために必要なコトモノ ・過電圧が引き起こす機器故障 ・なぜ基盤が発火するのか?など
応用講座3:フライトコントローラ
ドローンの中核をなす、フライトコントローラー(FC)。これをどうセッティングするかで飛行のしやすさはもちろん、撮影に合わせたセッティングや自動化したり、GoHomeをするための設定などを施すことが可能となります。FPVドローンのように自由度が高い反面、FCセッティングをマスターすることはとても重要になります。
・基盤(STmicro)とファームウェア ・BetaFlightとKiss(Fettec)の違い ・センサー基礎(Gyro/Accelerometer/Barometer) ・外付け機器追加搭載(受信機 /GPS/カメラ/VTX) ・モーター回転命令を出すまでのロジック ・Gyro/PID loop frequencyの役割 ・Ratesが決める機体回転速度 ・PIDとフィルターの基本的な理解 ・PID・フィルターのパラメタの意味と設定方法など
応用講座4:メンテナンス・保守
FPVドローンの運用する上で重要となるバッテリーマネジメントや機体のメンテナンスをする上で重要な点を解説しています。
・ドローンで用いるバッテリーの種類と特徴 ・リポバッテリーの充電方法と火災注意 ・クリーンビルドとフィルターの関係性 ・ケーブル劣化が引き起こすドローン墜落 ・プロペラのバランスと電流値の上昇など
実技講座1:シミュレータ練習
Liftoffというシミュレータを利用して、FPVの基本スキルの習得を行います。受講者専用のDiscord内では日々練習動画がアップされていて、リアルタイムにフィードバックを行うことで、FPV飛行の悪い癖やスティック操作のポイントを改善し、技術を高めていきます。講座内では実機中心のため、講座にきてシミュレータをやるのは非常にもったいないので家や開いている時間でのシミュレータ練習をおすすめしています。
ーLiftoff ・コース1:FPV基本操作(アクロモード) ・コース2:高度維持とスロットルタイミングの技術向上 ・コース3:機体傾斜方向とスピードコントロールの最適化 ・コース4:最適なライン取りを目指して ーLiftoff Micro Drone ・被写体を永遠に捉え続ける逆打ち操舵 ・スロットルエキスポ調整など
実技講座2:自作ドローン演習(目視)
DJIなどの機体が大量のセンサー類により、いかに誰でも操作できるものか、いかに自作ドローンが難しいかを実感していただけます。目視操作自体はある程度できればOKであり、講座ではそこまで行いませんが、自作ドローン特有の機敏さ・高回転モーターの調整方法、各種スイッチの役割を短時間で学びます。
・急スロットルと急ブレーキ ・前後移動と水平旋回 ・アクロ飛行でホバリングなど
実技講座3:飛行実技(FPV)
これを講座に沿ってマスターすることで、マイクロドローン撮影業務をサービスとして提供できる技術レベルを得ることが可能です。過去の受講生では平均的に3ヶ月目〜5ヶ月目におよそすべての項目を達成できます。
・FPVホバリング ・3段階高度変化調整 ・高度維持水平ターン ・目標物接近と後退 ・高度一定低空飛行 ・高度の上昇と下降の難しさの違い ・ライン取りのための機体傾斜方向 ・次点目標物を捉えるための逆打ち操舵 ・真ん中に戻してはいけないアングル飛行 ・複数舵同時操舵によるアクロバティック飛行 ・スピードコントロールと見えるラインどり ・機体サイズの違いが生む操作特性など
撮影講座1:FPV撮影基礎
FPV撮影は地上で用いるカメラやDJI製のドローン撮影とは手順も設定も撮影時の取り回し方も大きく異なります。FPVの特性やメリット、デメリットを理解しながら適切なセッティングを実際に撮影しながら学んでいきます。また、撮影できるだけではマイクロドローン撮影の特性を完全に理解できないため、Davinci Resolveを用いた編集や独自のスタビライズ調整も合わせて行います。
・FPV搭載するカメラ種類と使い分け ・広角レンズの特性の理解 ・スタビライズソフトの効果と違い ・撮影シーンごとのGoProセッティング例 ・Davinci Resolveの使い方 ・5分でできる撮影・編集カット・カラー調整など
撮影講座2:FPV(DJI)カメラワーク基礎
FPV撮影の特性とも言えるダッチアングルやドリー効果を具体的な事例とともに解説します。DJIカメラワークはおまけとして講座内で一緒に説明しています。
・リビールショット
・ダッチアングル
・エクストリームドリーイン/アウト
・ギャップ
・ローアティチュードなど
撮影講座3:FPVドローン応用撮影・演出
FPV撮影は現在ハリウッド映画でも用いられており、最新の現場では、FPVにシネマカメラを搭載し、引きの絵から寄りの絵になり、そのままハンドキャッチして人物を接写するために絞りやフォーカスをリアルタイムで調整して撮影するなどの事例が出てきています。YDLでは、FPVの新しい表現方法を模索し、それをトライする環境を講座内で提供しています。
・FPVドローンのハンドキャッチ&リリース ・バスケットボール、バイクの追撮 ・LED球体使用のFPVドローン演出 ・天地逆転3D移動など
営業講座1:業界理解・営業交渉
単にドローンを飛行するだけでは仕事にならないように、これだけのFPV知識と技術を習得しても仕事につながるわけではありません。各自の営業力やマーケティングが大前提であり、そのために業界構造から見積もり・単価感の理解、ワークフローの特性などを理解する必要があります。
・映像種類と予算と業界構造 ・FPV撮影・企画・演出の見積もり・請求例 ・マイクロドローンの突出した営業優位性 ・マイクロドローン撮影ワークフロー ・マイクロドローン撮影スケジュール ・インバウンド問い合わせ施策 ・アウトバウンド営業資料・動画 ・映像企画書作成例など
ここまで膨大な量のコンテンツがあるため、そもそも通常のドローンスクールのように2,3日でできるものではありません。また、単に練習場をあてがわれてFPVドローンの操作を学ぶだけでは到底お仕事につなげるのは難しいです。そのため、最低6ヶ月程度の時間が必要となります。しかし、上述した内容は一例であり、その他にも、「FPVドローンでできる撮影以外の仕事種類と事例」や「3Dプリンタを用いた製作講座」や「FPVアシスタント・FPVパイロットに求められる内容」「実践的撮影ワーク演習」「オリジナル機体開発」など講座内でどんどん提供していきます。
多くの卒業生も6ヶ月ですべてを理解できませんが、継続的にコミュニティに参加できたり、卒業後も現場同行したり、練習会に参加するなどしてさらに理解を深めています。「ちょっと国家資格を取っておこう」というレベルの生半可な気持ちでは正直難しいと思うため、人数を制限し少数精鋭で講座を行い、本気の人だけで運営しているのがYDL FPVコースです。
われこそは!という方の受講をお待ちしています!