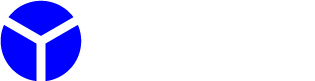2023年よりドローンの国家資格(一等・二等の無人航空機操縦者技能証明)が正式に規定されたことを受け、国家資格が取得可能なドローンスクールに通われている人が増えています。国家資格前までは、法的な有効性のない”民間資格”として各ドローンスクールが独自にカリキュラムを作成し、ドローンの基本的な運用から、測量・点検などに特化したコースなどが展開されてきました。
2024年2月現在、「ドローンの国家資格を所持しなければできないこと」はほとんどありません。将来的な一部の業務手続きとして必要になることは明白ですが、現状の多くの業務において必須資格ではないため、すぐに取る必要性が薄いと感じる人は多いと思います。僕も同じ気持ちですが、取らないで語るよりは取ってみた方が判断の信頼性が高いと思うので、取得してみました。ちなみに、一等25kgまで限定解除して取得しています。
ドローンの国家資格を取得するまでの流れ
最初に断っておくとめちゃくちゃ複雑です。ここでは全体の流れに留めるのみでそこまで詳細な手順は説明しません。他に色々わかりやすい説明などあるのでそちらを参照ください。それらを差っ引いて参考にしていただければ幸いです。なお、国家資格を講座として提供することを認定されたドローンスクールを経由するパターンです。僕はJMAドローンスクールで各種講座や実技修了試験を受けました。
一等二等無人航空機操縦士 国家資格を取得する流れ
まずは、全体的な流れから説明します。
| 1 | DIPS個人アカウントの作成(法人は不可なので新規作成した) | DIPS | 5分 |
| 2 | 登録講習機関で学科と実地講習を受講し修了審査で合格する | 実地 | 4日間 |
| 3 | 無人航空機操縦士試験申込システム(試験システム)のアカウントを作る (この際にdipsのメールと電話と同じにする) | ClassNK | 5分 |
| 4 | 試験システムで学科試験の申し込みをする 学科試験管理するプロメトリック社のID作成し学科試験を申し込む | ClassNK Prometric | 10分 |
| 5 | 代々木駅のプロメトリックセンターで学科試験を受験する | Prometric | 2時間 |
| 6 | 身体検査を受ける(免許証のアップロードでOK) ※25kg限定解除は病院の診察が必要なので後日行う。 | ClassNK | 1日 |
| 7 | 1.講習修了証明書 2.学科試験合格証明書 3.身体検査合格証明書の3つを持って「試験合格証明書の発行」を申請する | ClassNK | 1週間 |
| 8 | 7でもらえる試験合格証明書と実技講習修了証明書をDIPSにアップロードする | DIPS | 1週間 |
| 9 | 技能証明書(ドローン国家資格免許)が届く | 郵送 | -- |
| 10 | 25kg限定解除用の身体検査を受ける | 実地 | -- |
| 11 | 「試験合格証明書の発行」から同じ流れで免許証を更新する | -- | -- |
No.4-7までの手続きが酷く面倒で、申請後にリアルタイム反映されるわけではないので、申請しては待って…と放置していたら間があいてしまい、2023年12月には実技・学科試験のどちらも合格していましたが、実際に7の申請をしたのは2024年2月に入ってからでした。
一等試験の実技レベルはいかに!?

実地で行う技能試験について、終わってみた感想としては難易度は全く高くないです。技術というよりも、飛行前確認における声出しチェック(前良し、左良し、右よし、後ろ良し、上良し、下良しなど)、飛行後の機体点検などは、普段から業務としてドローンを扱っていない人には馴染みにくいルーチンがあるので業務未経験者はそこをしっかりと覚える必要はあるかと思います。
一等試験に必要なドローンの操作技術としては、
・GPSセンサーOFFの状態で
・基本的なホバリング
・同位置での旋回(ピルエット)
・高度変化を伴う移動
・8の字飛行(機首は進行方向)
ができるのであれば後は応用だったり、夜間や目視外などの内容によってはGPSもONになる場合もあるので普段業務でドローンを扱う人であれば、上述のお作法やチェックポイントのルーチンさえ覚えられれば数時間練習するだけでクリアできます。
まったくドローン飛行経験がない人や反射神経が酷く鈍い場合は相応に修練しないと取得は難しいのではないでしょうか。自作ドローンの製作やFPV飛行経験が1年以上ある人であれば、基本的な用語からルーチンはすんなりと入ってくるでしょうし、必要な飛行技術はあるので修了試験を突破するためのお作法をしっかり覚えられれば問題なく合格できるでしょう。
飛行前チェックや声出しルーチン、飛行後チェックなどは、やるべきことばかり(特に壊れやすい自作機ならなおさら)なので、事故や故障の発生確率を減らしたり、自分なりのルーチンを作る意味でも、やる価値はあると思います。自作ドローンにおいては、趣味でも業務でもメンテ不足で事故・クラッシュが頻発しますからね。YDLで新しく入ってくるメンバーも日々ドローンを壊しまくっていますが、壊れる原因のほとんどが飛行後の確認不足により「壊れやすい状態になっていること」や飛行前チェックが正しくできていないなど、異常な状態で飛行しようとすることに起因しています。
一等学科試験の難易度とは?
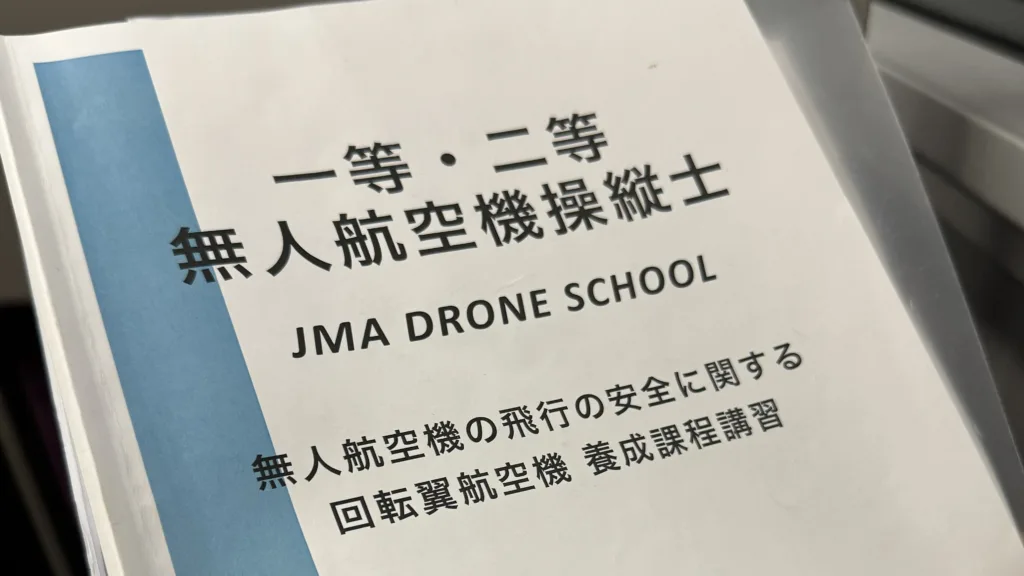
これは仮に経験者だとしても一通り勉強しないとまず合格することはないと思います。国家資格試験全般にも言えるかもしれませんが、引掛けとまでは言わないものの、問題文の解釈がわかりにくいものがあるため、事前に予習しておかないと解答に手こずるかもしれません。
僕の場合は出題範囲の内容をざっと確認し重要なポイントなどを登録機関の講習で教えてもらい、前日に一通りテキスト(国交省が公開している情報を講習機関がまとめたもの)を見直し学習を行いました。試験会場では、そこまで高速に解答したつもりは全くないですが、特段焦ることもなく解答をダブルチェックして10分以上は残して終了しました。2,3問、解答に迷う問題がありましたので後回しにして時間をたっぷり使ったと思います。全解答が終了すると、合格基準に達しているか否かがすぐに表示され、「合格基準相当」というような表示がなされたと思います。
一等・二等試験どちらにおいても、「計算式を伴う問題が出る」ということで、学科試験に難しさを感じる人がいると思います。確かに初見だとよくわからないこともあるのですが、公式を丸暗記しても問題自体は解けますし、自分で計算の意味を紐解いて理解するのもいいなと思います。
例えば、「回転数(RPM)の変化における仕事率(電力W)の違い」など、簡単に計算できるので自作ドローンを飛行する時にOSDに回転数RPMや電力Wや電流Aを表示するなどして、実際の数値と照らし合わせて検証してみるのも理解が進んで面白いと思います。全然計算式通りにはいかないけど笑。上空で突如モーター停止した時に被害が起きうる範囲(距離)はどの程度なのか、なども当てずっぽうな感覚的な安全マージンではなく、理論的な距離感を理解していることが運用をより楽にできるとも思いました。
ドローン国家資格はすぐに取得するべきか!?
技能試験も学科試験において、「知っている・理解している」ことも多々あるけど、新しい発見もあり、学んでいて意外と楽しかったです。強く思ったのは、「一緒に仕事する人には、最低限これくらいの内容は理解しておいてほしいな」ということです。一等二等レベルの技能・座学知識があることはコミュニケーションをする上でとても楽です。例えばアシスタントに入る人などがドローンの法務的なことはもちろん、最低限ピルエットくらいはGPS無しでもできるよねとか、モーターの特性やセンサー技術の基本的な理解だったり、気象に関するちょっとした予備知識があれば、より高解像度な話ができると思うからです。ディレクターやプロデューサーや営業チームのスタッフにおいては取得するインセンティブが薄そうですが、ここらへんの理解がある人がいたら、色々楽だなと想像できます。
とはいえ、冒頭にも書いたように「ドローン国家資格はドローン飛行にマストではない」ので急いで取得する必然性はまったくありません。なので取ろうかどうかすら考えていない人は取る必要はないと思います。それよりも、まずは撮影なり点検なり業務飛行を行ったり、アシスタントやサポートとして入ったりして業務経験を積んでいく方が、より国家資格取得の中で得る学びを吸収しやすくなると思います。4級アマチュア無線や3級陸特無線の資格でもそうですが、現実世界に活かせる面白い知識が結構あるので、馬鹿の一つ覚えで詰め込むのではなく、理解して取得するほうが有意義だなと思います。
迷っているなら今のうちに取っておくのはあり!
すでに業務経験が多少なりともあって、取ろうかどうしようか迷っている人であれば、今のうちに(経験者優遇の措置があるうちに)取っておいたほうが良いと思います。(※今年のどこかのタイミングが経験者優遇がなくなり、取得するにあたっての講習受講期間がとても長くなるという話を聞きました。)また、上述のようにドローンの基礎的な仕組みや安全運用を一通り体系立てて理解することができるし、運用者とのコミュニケーションが比較的容易になると思うからです。
一部のクライアントや飛行場所(例えばケースとして以前あったのは代々木体育館など)、自治体など保守的なお客さんからの依頼の場合に「ドローンの国家資格が必須」条件となるケースも存在します。法的には不要であっても、一定の知識・安全レベルを担保したいがために、国家資格をマスト条件とすることはありえる話なので、機会損失をしたくない場合においても国家資格取得は有効です。個人的には、ここらへんは交渉でいかようにもなるかなと思いますが。
お仕事する以上、必ず相手がいます。本来は相手が安心できる材料が提示できてさえすれば何でも良くて、その一つとして国家資格は最低限の知識・技術を提示できるものとして使えることもあると思います。(僕自身はドローン国家資格を活用できたことはないですが…笑)
FPV自作ドローンこそ網羅的な理解や安全運用方法を確立するべき
FPV自作ドローンは目視外飛行など、場合によっては目視飛行に比べてリモートコントロールでより安全に運用できる飛行方法ですが、型式認証を取れるような機体やDJI製のドローンと比べれば機体としての信頼性が非常に劣るし、冗長性やフェールセーフ機能がないことが多いので、より安全に飛行するためには運用でカバーする必要が出てくると思います。DJI製ドローンですら飛行前・飛行後点検をするのを義務付けられているのに、GPSや気圧センサーすら積んでいない自作ドローンで点検や確認を行わないなんていつか事故るに決まっているじゃん、と思ってしまいます。
資格ホルダーのように『国家資格取得』自体を目的にする人は論外ですが、基礎的なドローン運用方法を理解する機会としてはとても良いと思うので、迷われている方は早めにとっておくのがいいのではないでしょうか。
ちなみに、FPVドローンの業務運用で必須となる国家資格として「陸上特殊無線技士」があります。同資格についてや必要な業務運用の始め方については以下を参照してください。